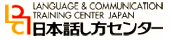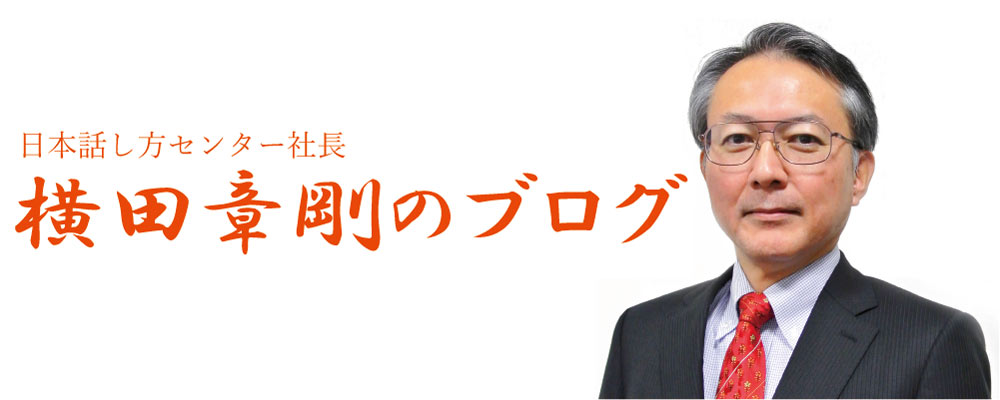2020年4月14日「主張-論拠-事実」を整理しましょう
★話す内容を分けて整理する
前回は『物事を分けて考える』ということについて書きました。
今回は、分けたものをどのように整理して話せばよいのか、ということについてお話します。
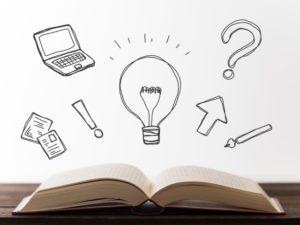
会議などで話すときは、論理的に話した方が伝わりやすいですよね。
論理的に話す出発点は、物事を分けることだ、ということを前回お話しました。
例えば、人事部が「社員向けにマナー研修を実施したい」と考えたとします。
このままだとそれを聞いた他の部から「今は人が足りなくて現場は大変なんだ。教育に割く時間なんてないよ」などと反対意見が出るかも知れません。
★『主張 - 論拠 - 事実』
なので、「マナー研修を実施したい」ということを、パーツに分けて議論するようにします。
その分け方が、「主張 - 論拠 - 事実」です。
「主張」は「マナー研修を実施したい」ということそのものです。
この「主張」だけを言うと、聞いた人は賛成、反対の何れかを直感的に判断してしまいます。
賛成、反対を感情で判断してしまうので、議論も感情的なものになり落としどころが見えなくなります。
なので、この「主張」に「論拠」をつけます。
「論拠」とは、なぜそういう主張をするのか、という理由です。
この例だと「取引先で社員の不適切な振る舞いをよく見かけるから」というようなものが論拠です。
この論拠があると、議論は感情ではなく、論理で進めることができるようになります。
従って、論拠は非常に大事なものなのです。
しかし、実際の会議や職場での会話では、この論拠を言わないことが驚くほどあります。
そうした場合、「マナー研修をやりたい」と聞いた人は、「きっとこういう理由だな」と頭の中で勝手に論拠を推測して作ってしまうのです。
しかし、その論拠は聞き手がそれぞれ勝手に思い浮かべたものなので、主張する人が思い描いている論拠とは異なる場合があります。
そうすると、議論が後でずれたりして、これも収拾がつかない原因になってしまいます。
逆に、論拠をきちんと話せば感情的な議論にならず、論理的に話を進めることができます。
ですから、論拠は非常に大事なパーツです。
ところで、論拠として、「取引先での振る舞いが良くない」と聞いた時に、「本当にそうなのか?」と疑う人もいるでしょう。
そうすると、せっかく論拠を言っても、納得してもらえず、論理的な議論ができなくなります。
そこで、本当に論拠が成り立つのか、と言うことを示す「事実」が必要になります。
この例だと「顧客満足度アンケートで、3割の回答者が我が社の社員のマナーが不適切だと指摘している」などが事実になります。
★タテの論理をつなげる
この「主張 - 論拠 - 事実」がきちんとつながっていると、聞き手が納得する、論理的な話ができます。
これをロジカルシンキングの世界では「タテの論理」といいます。
もし主張~事実がきちんとつながっていないと、聞き手は、「本当にそうなの?」という反応になります。
もし話をしていて、相手に「本当?」と言われた時は、このタテの論理がきちんとつながっていない、と思ってください。
このタテの論拠のキーワードは「なぜ」です。
なぜそういう主張をするのか、を考えると論拠が出てきます。
そして、なぜそれが論拠だと言えるのか、を考えると事実が用意できます。
この準備をしておけば、より説得力のある、論理的な話ができます。
ぜひ意識してみてください。
★分かりやすい話し方を身につけましょう!
論理的に話せるようになるには、それなりにトレーニングを積むことが必要です。
しかし、独学でそのトレーニングを行うことはかなり大変です。
このトレーニング方法でよいのか不安に感じることもあるでしょうし、トレーニングが継続できない、ということもありがちです。
従って、論理的に話す訓練を積むには、話し方教室に通うことをぜひお勧めします。
日本話し方センターのベーシックコースでは、3ヶ月間、余計なことは言わずに必要なことだけを具体的に話すトレーニングをしていただくコースです。
今回お話したこともこのコースを受講することで確実に身につけていただきます。
ぜひご受講ください!